ケイネス先生の聖杯戦争第六十局面
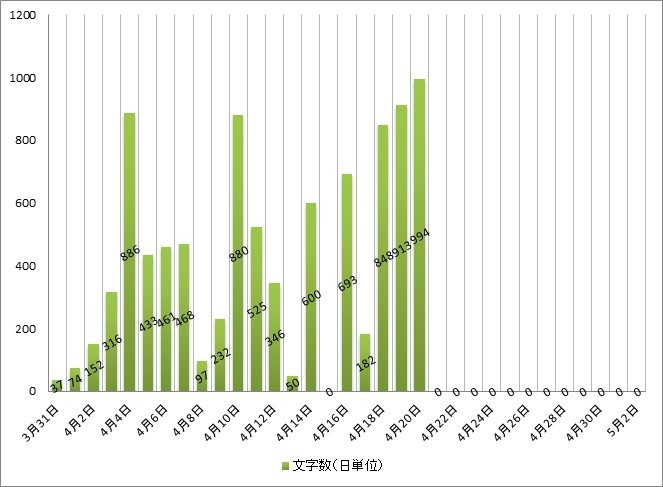
一方ランスロットは黒セイバーと対峙していた。愕然とした、呆然とした、出来の悪い冗談を前にしたかのような、ひとつに断じ難いその感情。「王よ……我が王……」力なく、呼びかける。夢にまで見たはずの光景だった。こうなることを、バーサーカーに身をやつしてまで望んでいたはずだった。愛にも責務にも生きることができなかったこの惰弱な魂を、迷いなき一刀をもって断罪してほしかった。他の誰でもない、彼が忠誠を捧げた唯一の偉大なる王に。狂おしいほど、そればかりを渇望していたのに。「あぁ、なんたる……そこにあなたはいないのですね……」騎士王アルトリアの魂はすでにこの世になく、あるのは邪悪なる意志によって姿かたちだけを模倣された存在だけであった。ランスロットは、烈火のごとく怒り狂うべきなのだ。このような冒涜を、主君への侮辱を、決して許してはならないはずなのだ。だが――だが。ランスロットという男にとり、王の存在は大きすぎた。たとえ本質の伴わぬ張り子であろうとも、その姿をしているというだけで、自失呆然するには十分すぎた。すぐに剣を構えるべきなのに。裂帛とともに斬りかかるべきなのに。どうしてもそれができなかった。王を殺したいなどと考えたことなど一度たりともなかった。ただ裁かれたいだけだった。だが、寛大にして清廉なる王がこちらに慈悲をかけてしまう可能性を排除するために、狂化された意識のなかで彼女に襲い掛かっていたにすぎない。理性を取り戻した今、もはやそのような不敬もできなくなった。王を倒さねば大聖杯に至れぬのに。至らねば世界の破滅すら引き起こされかねないというのに。どうしても、ランスロットは王に剣を向けることができなかった。ただ、魔力放射によって高速接近してくる模造聖剣の切っ先を、歓喜と罪悪感をもって見つめ続けることしかできなかった。「ディルムッド……マスター……すまぬ……すまぬ……」己が霊核が貫かれる感触に、ランスロットは救いを得た。得てしまった。そのことが、新たな呪いと罪になって、その魂を徹底的に穢していった。狂化スキルとは異なる、真正の邪悪存在へと。